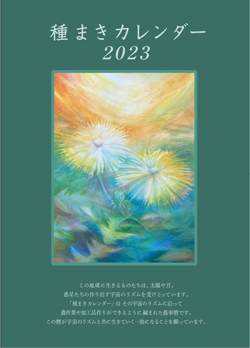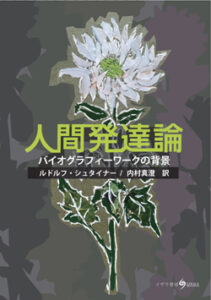シュタイナーの感覚論にもとづく発達心理学の観点から
2,800円 (税別)
248ページ
A5判
2023年9月発売
ISBN : 978-4-7565-0158-5
ネットショップで購入
内容
いつも必ずどこかにいるどこか脅えた子供たち。
彼らは、自分は歓迎されていないのではないかと、あるいは、自分は見捨てられているのではないかと、あるいはまた、自分は仲間外れにされているのではないかと感じています。そして、そのように感じている子どもたちは皆、暮らしのなかへとまっすぐ歩を進めることをためらっているのです。
そんな子供たちを心配する保護者含め周囲の人たちへと、本書は、まなざしの意味効用、心構え等々、デリケートで小さいけれど、とても重要なことを教えてくれる内容です。
出版社から
初版第一刷:p68の8行目 ~ p69の8行目の文章が重複しておりました。
申し訳ないのですが、その部分を除いてお読みください。
お詫びして訂正いたします。
四つの身体感覚(生命感覚、触覚、運動感覚、平衡感覚)のうち例えば触覚は、世界との愛に満ちた触れ合いなどを丁寧に経験することが、抗不安に繋がり、神経症的多動的情緒不安定状態を改善解消の方向に向けるという本書趣旨は大勢の共感を呼ぶのではないでしょうか。
聞き分けなく反抗的に振舞う子どもは、実際にはただ何かに脅えているだけで、不安に襲われ、鳥篭の中で暴れている小さな小鳥のようなもの。では自分たちに具体的に何ができるか考えてもなかなか解決策はみつからないかもしれないけれど、毎晩五分間だけその姿、小さな鳥籠が窮屈で暴れている様を思い浮かべる練習をすることで、何かが変わるはず・・・。
周りの人々(教育者、父母など)が子どもたち一人ひとりに関心を持ち、その奥に秘められたそれぞれの子ども自身の輝き・尊さを信じられた時、その眼差しの下で子どもは変わります。
目次
1、教育実践に関する基本的な事柄
夜が助けてくれる
天使が応えてくれる?
橋の番人からの問いかけ
魂にとって身体が冷たすぎるときは
冷たい頭と温かい魂
道徳教育とは?
創造的な知覚プロセス
模倣しつつ善きものを求める
2、生命感覚を探る
この章のはじめに
基本的な心地好さについて
生命感覚についての、その他の事柄
肯定的な静かな覚醒状態と善きものの体験
生活リズムと自分という存在への信頼感
落着きのない‐興奮しやすい子ども
呼吸を解き放つために生命感覚を育む
教育と自己教育 ― 寛容の姿勢について
3、触覚を探る
感覚器官としての皮膚
触覚による知覚はどのような性質を持っているか
神的感情の浸透
触覚と関心 ― 相違の体験、身・魂の共振、存在の確認
人間学と教育実践
理解するということは?
世界との愛に満ちた触れ合い
近しさと痛み
空間的な境界を持つ身体的な自己
地上への誕生
教育と自己教育 ― 心配り
不安を抱えている子どもの潜在的トラウマ
身体的感覚と社会的感覚 ― 後天的な不安
不安げな‐ためらいがちな子ども ― 幾つかの観察
よい睡眠とよい目覚めに向けての準備
教育と自己教育 ― 肯定的な視線
不安げな‐ためらいがちな子ども ― 幾つかのさらなる観察
まとめ ― 落着きのない子ども、不安げな子どもとは、どうかかわればよいか
4、運動感覚、平衡感覚を探る
この章のはじめに
自分自身の自由な魂を感じること
自律の感情
隠れた芸術家
魂の繊細な調整について
動きのなかで一つの「まとまり」をなしている魂
感情移入と思いやりの心
誤った診断 ― 厳しい発達条件について
寂しげな‐沈みがちな子ども ― 潜在的な運動感覚障害の特徴
さまざまな要因 ― 幼児期における模倣活動に関して
天使が触れる ― 子どもが抱いている無意識の郷愁
寂しげな‐沈みがちな子どもとはどうかかわればよいか
率直な分かりやすい言葉、内容の詰まった身ぶり
教育と自己教育 ― 思いやりの心
平衡感覚
解放された腕と手の働き
平衡感覚と判断力 魂の平衡(バランス)と公正感覚
恩寵(おんちょう)としての歩行能力 ― 平衡感覚の役割
魂のバランスと、自分の価値を認める感情
まとめ ― 寂しげな‐沈みがちな子どもたちの指導に向けて
おわりに ― 教育と倫理